2017年3月18日号(第573号)
今週のテーマ:突撃ラッパは何度吹き鳴らされたか |
| 元海軍軍属でカウラ事件のサバイバーである今井祐之介さん(今年で97歳)をインタビューするために、伊豆半島の小さな美しい街へ行ってまいりました。 |

今なお雪深い北信濃の書斎から花咲き乱れる伊豆半島へGO!
注:雪上車で高速道路を走ったわけではありません(笑)。 |
今井さんにお目にかかるのは、これで4度目になるでしょうか。毎回お目にかかるたびに、じっくり腰を据え、一日がかりで事件に関するインタビューをさせていただいてきました。
当然、大方のことは既に聞かせていただいており、アウトラインに関しては大きな聞き漏らしはないと考えています。
では今回、なぜもう一度改めて今井さんをインタビューしなければならなかったのか。
それは、「カウラの暴動に先んじて突撃ラッパは何度吹き鳴らされたか」という質問に向き合っていただくためでした。 |

インタビュー当日は幸い好天に恵まれ、富士山がきれいでした。 |
カウラ事件発生時、突撃ラッパが鳴り響き、それが暴動開始の合図となったことは周知の事実です。
ラッパを吹いたのが零戦パイロットの豊島一(捕虜としての偽名は南忠男)であることも、多くの証言からわかっています。
このとき彼は何度ラッパを吹いたのか。一度なのか、二度、あるいはそれ以上なのか。
これをお読みになって、
「ラッパが一度鳴ろうが二度鳴ろうが大差ないのでは?」
と思った方もいらっしゃることでしょう。しかし実のところ、そこにはもう少し本質的な問題が含まれているように思われるのです。
私がそう思う理由の一つを下に記します。
旧日本軍の陸軍と海軍は仲が悪かったというのは有名な話ですが、仲の良し悪しは別としても、両軍には物の考え方から、暮らしぶり、行動に至るまで実にさまざまな違いがありました。
例えば陸軍での一人称が「自分」だったのに対し、海軍のそれは「わたくし」でした。
敬礼の仕方などに代表される所作の多くも、陸軍と海軍では異なっていました。
感情面でも、至近距離まで近づいて一対一で殺し合う陸軍と、遠く離れた船と船の間で爆弾の応酬をする海軍とでは、「敵に対する“個人的な”憎悪」がどの程度生じるかという点で大きな差があったと考えられます。 |

数か月ぶりにお会いした今井祐之介さんと。
今年で97歳になられることが嘘のような頭脳明晰さでいらっしゃいました。 |
今回問題となる「突撃ラッパの吹き方」の場合、陸軍では二度(あるいはそれ以上)繰り返して吹いたのに対し、海軍では一度しか吹かなかったと言います。
その理由は、陸軍では無数の兵士たちが広い範囲に陣を張っていることが多く、一度だけでは聞き漏らす危険があった。対する海軍では、基本的に船という限定された広さの上に全員が揃っているのが基本で、ラッパを一度吹けば皆に聞こえたからです。
さて、ここで問題となるカウラ捕虜収容所の場合、陸軍出身者と海軍出身者がごちゃまぜ状態で収容されていました。
しかし暴動発生時の捕虜数は圧倒的に陸軍が優勢。
一方、突撃ラッパを吹いた豊島一は海軍出身。
この状況下で、突撃ラッパは何度吹き鳴らされたのか。
今回、このテーマを掘り下げることによって、暴動発生当時(昭和19年8月5日)の日本兵捕虜たちの「力関係」を改めて考えてみたいと思います。
この件についての詳細は、5月14日(日)に東京都内で開催を予定している「カウラ事件物故者を偲ぶ講演会」にて発表したいと思います。
クローズドの講演会(既にほぼ満員)ではありますが、ご関心のある方は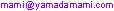 までメールにてお問い合わせください。ご期待に添えない場合にはご容赦願います。 までメールにてお問い合わせください。ご期待に添えない場合にはご容赦願います。
ではでは♪ |
▼・ェ・▼今週のクースケ∪・ω・∪

山小屋の庭には現在もまだ
これだけの雪が残っています。
(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |
|
|
