2016年12月3日号(第563号)
今週のテーマ:初雪とクリスマスツリー点灯式 |
山小屋のある北信州では11月9日に初雪、次いで23日にシーズン二度目の雪が降りました。
とはいえどちらも根雪にならず、今日はまだ秋枯れの大地が広がっていますが。
写真は二度目の雪が降ったときに庭を撮影したものです。 |

11月23日に降った雪。翌日には融けてしまいました。

このオンドリ兄弟は2016年生まれ。
雪を見るのは初めてです!

例によって純白の帽子とショールがお似合いなお地蔵さま♪ |
次いで11月25日には、東京都港区高輪台の明治学院大学でクリスマスツリー点灯式が執り行われました。
これは、今年献堂100周年を迎えたチャペルの前にある大きな芝生で行なわれる、毎年恒例の行事なんです。
せっかくなので、今年は娘と孫娘(1歳8か月)を誘って行ってみました。
色々と物事がわかるようになってきた孫娘は、キャンパスに降り積もったイチョウの葉っぱを拾ったり、港区内と長野県小諸市(※注)の小学生たちによるクリスマスソングの合唱に聞き入ったり、点灯のカウント・ダウン(10、9、8、7、6……)を唱和したりと、一連のイベントをことのほか楽しんでくれたようでした。
思えば孫娘にとって、この世は初めてのことで満ちているのですよね。
世界を見る目がキラキラ輝いていて、まるで大昔の私自身を見るみたい。
ひるがえって私自身はどうかと言えば、年々経験量が膨大になってゆく一方で、「初めて」のことは減るばかり。明学のツリーの点灯式もこれで4~5回は見たでしょうか。
とは言え、点灯式自体には慣れていても、孫娘と過ごすクリスマスツリー点灯式は今回が初めての体験なわけですから、見方によっては、この世はいつまでだって新鮮な体験と驚きに満ちているとも言えます。
要するに人生の後半で楽しむべきは、物的・量的な喜びではなく質的な喜びだということでしょう。
最近は心から思うんですよ。歳をとるのはかなり楽しい体験だな、と。
なにしろ若いときには見えなかったものが少しずつ見えてくるのですから……。
肉体的な視力は衰えても、心の眼は少しずつ開いてゆく。そんな歳の取り方をしたいものです。 |

点灯した直後のツリーと、孫娘と私。

明治学院大学の正門側から見たツリーと記念館(2階建ての重厚な建物)。

小さなツリーに近づいて見つめる孫娘。

大きなツリーの根元付近まで潜り込んでみました。
なお1年を通じて芝生内に立ち入ることが出来るのは
クリスマス点灯式前後の1~2時間だけのよう……

大きなツリーの周囲を取り囲む小さなツリー。
素朴ですが、商業的なツリーにはない美しさがあります。 |
なお、先週末に長野市内の北堀公民館で開催していただきました講演会(「戦争と日本人~歴史から消された世界最大級の日本兵捕虜脱走事件」)は、朝陽公民館に引き続き、お蔭さまで無事に終了いたしました。
今回もカウラ事件のさまざまな側面を掘り起こし、現代日本が抱える問題にもつながるテーマとして皆さまとシェアできましたことを嬉しく思います。
日本では往々にして、講演会の最後に質疑応答の時間を設けても、恥ずかしいのかなかなか手が挙がらないのですが、今回は次々に質問が飛び出し、実に活気のある時間となりました。
ご来場くださった皆さま、主催者の皆さま、特に公民館長さんと、7年越しで本企画を温めてくださいましたコーディネータの千野長重さんご一家)、そして講演会の広報を出してくださった信濃毎日新聞さんにも深く御礼申し上げます。
この講演会、シリーズにして各地で続けられたらいいですね。
「ぜひわが町でも!」とお考えの方は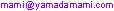 までご一報ください。 までご一報ください。
お待ちしています。 |

北堀公民館にて。手書きのバナーがいい味を出してます。

講演会中のひとコマ
(左後ろの「声かけよう向こう三軒両隣」の標語も、公民館らしくて素敵ですね!) |
2016年も残り1か月を切りました。
何かと忙しい日々が待っていますが、お風邪などひかないよう気をつけて健やかにお過ごしくださいませ。
ではでは♪
※長野県小諸市と明治学院大学は、本学の第一期卒業生である島崎藤村のご縁がもとで2006年に協働連携に関する基本協定を提携。毎年のクリスマスツリー点灯式には小諸の小学生が訪問し、可愛い歌声を聞かせてくれます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
▼・ェ・▼今週のクースケ&パンダ∪・ω・∪

初めて見る雪に大興奮し、
叱られても叱られても雪を
食べる食いしん坊クースケ
(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |
|
|
