2009年3月9日号(第325号)
今週のテーマ:高尾山の天狗の火渡り |
★ 仏教エッセイ ★
 |
真言宗のお寺・金剛院さんのウェブ上で『仏教一年生』と題したエッセイを連載中です。第11回(3月3日更新)のテーマは「座敷わらし」。左のロゴをクリックしてページに飛んでください。 |
|
 |
ただいま発売中の「月刊みんぱく」3月号(国立民族学博物館・刊)に、山田真美の巻頭エッセイ「インド数学の思考」が掲載されています。この冊子を抽選で3名の方にプレゼントいたします。
ご希望の方は、 (1)お名前(本名)、(2)ハンドルネーム、(3)ご住所(冊子の郵送先)、(4)山田真美へのメッセージを明記のうえ、3月16日までにmami@yamadamami.com までご応募ください。※メールの件名は「月刊みんぱく」でお願いいたします。 |
|
今日のタイトルをご覧になって、
「高野山の天狗」
とすんなり読んでしまった方、恐れ入りますが目をこすって、タイトルをもう一度よ〜くご覧ください。
今日これからお話するのは、高野山ではなく高尾山のことですので、そこのことろ、決してお間違いなきようお願いいたします(笑)。
高尾山と言えば、首都圏を代表するハイキングのメッカであり、東京で最も標高が高いところにあるビアガーデンでもつとに有名ですが(笑)、実は、ここの山頂にある薬王院というお寺は、成田山・川崎大師と並ぶ真言宗智山派の三大本山のひとつ。
ここでは毎年この季節に、火渡りの儀式が行なわれるのです。
……というわけで昨日(3月8日)は、その火渡りを見に高尾山へ行って来ました。 |
 
「高野山」と「高尾山」は名前だけでなく、乗り物の形までよく似ています。左が高野山の
ケーブルカー、右が高尾山のケーブルカー。勾配は高尾山のほうが急だそうです |
高尾山薬王院の本尊は飯縄大権現といって、私の故郷・長野市に聳える飯縄山にそのルーツを求めることができます。
戦国時代に詳しい方はご存知のように、上杉謙信の兜の前立ちが、まさにこのこの飯縄大権現ですよね。
(※よそ様のサイトで恐縮ですが、謙信の兜の画像はこちらをご参照ください)
飯縄大権現と言えば、不動明王の身体に烏天狗の嘴(くちばし)を持つ、見た目は恐ろしげな風貌の神。
神格的には不動明王・迦楼羅天(インドのガルーダ神が仏教に取り入れられた姿)・荼吉尼天(インドのダキニが仏教に取り入れられた姿)・歓喜天(インドのガネーシャ神が仏教に取り入れられた姿)・宇賀神(穀物や食物を司る日本の古い神で、後に弁才天と習合)・弁才天(インドのサラスヴァティー女神が仏教に取り入れられた姿)が合体した、かなり複合的なもののようです。
そして、この飯縄大権現の眷属(手下・一味のこと)が、何を隠そう「天狗」なんです。
だから、高尾山の中はどこへ行っても天狗だらけ。たとえば↓こんな強面(こわもて)の天狗がいるかと思えば、 |
  |
| 眩しいほど金ピカな天狗↓も。 |
  |
| そうかと思えば↓こんなゆるキャラ風もいたりして(笑)、なかなかどうして、バラエティー豊かですね〜。 |
 
こんな天狗なら、むしろペットにしたいかも(笑) |
なお、上に並べた6枚の写真は、すべて左右の天狗がペアになっています。
3組とも、向かって左は嘴(くちばし)の尖った烏天狗(からすてんぐ)で、右は鼻の高い大天狗。
持ち物は、烏天狗が剣、大天狗が羽扇と異なりますから、容易に見分けがつきますね。
このうちの大天狗は、ありとあらゆる天狗の中で最強の天狗だそうです。
いわばラスボスみたいな天狗だと思えばいいのでしょう。
ちなみに天狗のルーツに関しては諸説あるようですが、烏天狗のルーツはガルーダと呼ばれるインドの神さま、大天狗のルーツは日本神話に登場するサルダヒコ(猿田彦)だと言われることが多いですね。
このうちのサルダヒコに関しては、私も、7年前に出版した『夜明けの晩に』の中でかなりのページを費やして書いています。ご興味がおありの方は、是非ともご一読くださいませ♪ |
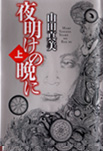 
『夜明けの晩に』詳細はこちら |
さて、昨日の大祭では、山伏と僧侶による大護摩供、火生三昧(かしょうざんまい)供、それに信徒の身体健全を祈願する火渡り修行などが行なわれました。
なにしろ山伏や信徒のあとで一般の人も火渡り修行を体験できるとあって、会場には何百人、何千人という善男善女が詰めかけてズラリ長蛇の列!
外人さんも、かなり大勢いらっしゃいましたよ。見た目だけでは日本人かどうかわからない東アジア系の方々も含めれば、昨日はビックリするほど多くの外国人の方が火渡りを体験なさったんじゃないでしょうか。
そう言えば高尾山はフランスのミシュラン(ガイドブック)にも紹介されているぐらいですから、ひょっとしたら、この火渡り祭りは海外での知名度バツグンなのかも知れません。
それでは、昨日の一般の人々による火渡り修行の様子を簡単にご紹介しましょう。 |

筵(むしろ)に置かれた塩の上に立ちます。山伏は
信者の背中をドンと叩いて「気」を入れるような所作
をします(後方の山までズラリ並んだ長蛇の列は、
火渡りの順番を待つ善男善女たち)
   
   
   
   
「おん ばろだや そわか〜 おん ばろだや そわか〜」という真言の大合唱が降りしきる中を、
善男善女たちはみずからの健康などを祈願しながら、裸足で黙々と熱い土の上を歩きます

無事に歩き終えると、再び筵の上の塩を踏みます |
ちなみに、火渡りのあいだ間断なく唱えられていた「おん ばろだや そわか」という謎のような言葉は、水天の真言です。
「水天」は、日本では十二天のひとつで、神格としては水神あるいは龍神ですね。
今でこそ割と地味なイメージに落ち着いてしまった感のある水天ですが、もとはヴァルナ神と言って、インドとイラン(ゾロアスター教)の古い神話では、ともに宇宙原理を司っていた最高神でした。
その後、ヴァルナはインド神話の中でも他の神々に地位を奪われ、今ではあまり注目されることのない存在になっています。
(神々の世界にも栄枯盛衰というか、流行りすたりがありますから。人間社会とまったく同じように)
もっとも、そんな小難しい話を引き合いに出すまでもなく、
「火渡りの際に火傷をしませんように」
という意味で水天の真言を唱えることは、実に理に叶っていると言えるわけですが。 |
 
  |
それにしても、天狗とか修験道とか、これまた本当に不思議な「あなたの知らない世界」ですよね!
高尾山薬王院は、初めから今のようなお寺だったわけではなく、奈良時代に行基菩薩によって開かれたときの本尊は薬師如来でした。
しかし14世紀に入ると、高尾山の中興の祖となる俊源大徳が飯縄大権現を新たに本尊として据え、この地を修験道の道場としたそうです。
薬王院には、いかにも仏教寺院らしい建物もあれば、朱塗りの鳥居もあり、まさしく神仏混淆を絵に描いたような不思議空間が広がっています。日本の宗教史のなかで高尾山が担ってきたユニークな役割がしのばれる、実に興味深い空間です。
……というわけで、またひとつ日本文化の奥深さに触れることのできた春の1日でした。
ではでは♪ |
▼・ェ・▼今週のブースケ&パンダ∪・ω・∪

パンダを上から見たところ。ザンバラ髪の落ち武者
みたいでしょ?
(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |
|
|
